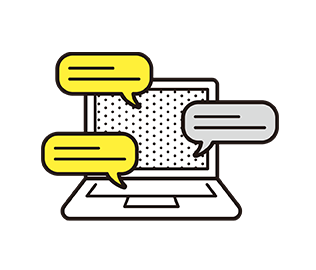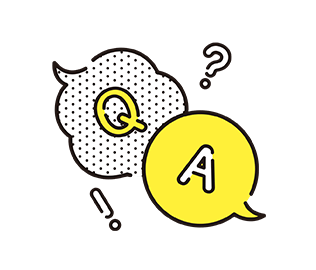- トップ
- 幼児期の「なぜ?」は知的好奇心の芽。上手に伸ばすために大事な3つのポイント
幼児期の「なぜ?」は知的好奇心の芽。上手に伸ばすために大事な3つのポイント
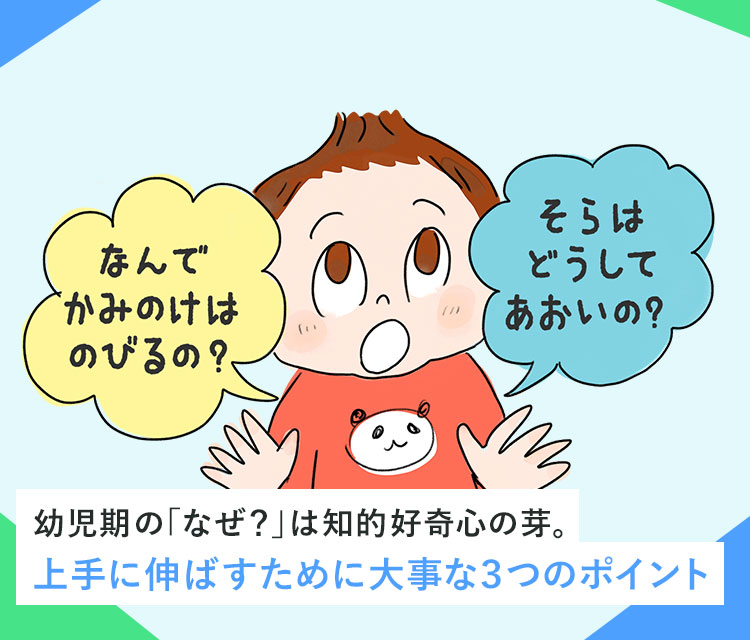
この記事は2分で読めます
最近、こんな様子ありませんか?

大人も「おっ」と思うような素朴な疑問は、知的好奇心のサイン。この時期に、おうちのかたが疑問を受け止め、お子さまがもっと考えることを楽しめるようになれば、芽生えた好奇心を上手に伸ばしてあげられます。
幼児期は、
「なぜ?」と考えられる時期

2・3歳頃は「これ何?」と名前を聞きますが、年少さん以降は「なぜ?」「どうして?」と理由や原因を聞く質問が増えてきます。幼児期は、変化や違いに気づくようになり、ものごとのしくみが気になる時期。じーっと観察して特徴に気づいたり、見て聞いてさわって五感を使いながら、いろいろな発見を楽しみます。頭の中でいろいろなことを考え、体験を通して納得したり、さらに発見をすることで「もっと知りたい」という好奇心が育ちます。
「でも素朴なギモンって、答えるのがすごく難しい…」「間違えたことを教えたらどうしよう」というかたがいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫!大事なのは、正解を教えることではありません。
知的好奇心を上手に伸ばす
ために、大事な3つのこと
年中さんの「なぜ?」「どうして?」には、答えがわかることよりも、疑問を一緒に楽しみたいという気持ちと自分で納得したいという気持ちがあります。知的好奇心を伸ばすために大事なことは、おうちのかたの共感と促しなんです。
ポイント1「なぜ?」を共感し、
受け止める

お子さまにとって、おうちのかたに聞いてもらうことはうれしいこと。「フシギだね」「おもしろいギモンに気づいたね」と気づいたことを認めたり、考える姿勢を肯定してあげることが「いろんなことが知りたい」という前向きな気持ちや、さらなるギモンをもつ姿勢につながっていきます。
ポイント2観察や発見を通して、
自分で考えることを促す

ギモンは出てきたけれど、お子さまが「どこから考えたらいいかわからない」「何をみたらいいかわからない」と、考えるきっかけが必要なときがあります。そんなときは、「ほかのものと比べてみよう!」という声かけなど、気づきにつながる視点やヒントがあると、考えることがもっと楽しくなります。
ポイント3実際の体験を通してわかる

本や動画を見る中でギモンを感じたり学んだりしたことを、実際の体験を通して理解できるとさらによい経験に。比べたり観察したりする"観点"が身についたうえで、実際に見たり聞いたりしたときに、学びはより充実したものになります。
「自分で考える力」は将来に
つながる大事な力
幼児期の素朴な「なぜ?」を見逃さず、知的好奇心を伸ばしていくことは、小学校以降に大切な「自分で考える力」につながります。たとえば、「なぜ?」のギモンを解消するために、注意深く見聞きすること、じっくり眺めて比べることで、じっくりと考える力が養われます。また、ギモンが解消して「そうなんだ!」と達成感を得ることや「もっと知りたい!」と何回も挑戦する体験は、自分から学ぶ姿勢や学習意欲につながります。
おうちのかたが教えなくても
自ら学び好奇心を伸ばせる教材って?
〈こどもちゃれんじ〉なら、年齢に合わせて自分から好奇心をぐんぐん伸ばせる教材をお届けします。
毎月お届けする教材について
詳しくはこちらから
-
2025年4月2日~
2026年4月1日
生まれ -
2024年4月2日~
2025年4月1日
生まれ -
2023年4月2日~
2024年4月1日
生まれ -
4月から年少さん2022年4月2日~
2023年4月1日
生まれ -
4月から年中さん2021年4月2日~
2022年4月1日
生まれ -
4月から年長さん2020年4月2日~
2021年4月1日
生まれ -
現在年長さん2019年4月2日~
2020年4月1日
生まれ
いきなりはちょっと…というかたには、無料の体験見本もご用意していますので
一度お子さまと試してから検討いただくこともできます。
入会金0円・送料別途不要
入会のお申し込み- トップ
- 幼児期の「なぜ?」は知的好奇心の芽。上手に伸ばすために大事な3つのポイント